自治政策講座「誰も置き去りにしない自治を目指す」

令和元年5月21日(火)に、横浜市の万国橋会議センターで開催された自治政策講座「誰も置き去りにしない自治を目指す」を受講してまいりました。
富山市議会のホームページから政務活動報告書もご覧になれますが、このブログにも掲載しておきます。
研修会・研究会の内容
1.どこでも起こる土砂災害に備える(講師:(財)砂防・地すべり技術センター研究顧問 池谷 浩氏)
- 内容:災害現場に入って防災研究を行った立場からの講義
- (ア)土砂災害といっても様々な種類があり、どのような自然現象がどのような形で人間社会に被害をもたらしたか、過去の事例から自分たちの町ではどのような災害が起こり得るか学び、対策を行う必要がある。
- (イ)過去に例がない自然現象の増加(雨の降りかたが新たな時代に入ったと言える)や人間社会が自然現象に近づいていること、さらに高齢化ということを認識する必要がある。
- (ウ)ハザードマップが命を守るのではなく、活かして避難しなければならない。また、避難命令の空振りも起こり得る。だが実際に起これば大変な被害となっただろう。
2.AIの利活用と自治体
講師:東海大学政治経済学部政治学科教授 小林 隆氏
- 内容:AI研究の第一人者であり、自治体職員としての経験もある立場からの講義
- (ア)AIの導入は不可避であり、日本が先進国の中で最も遅れている。また、マイナンバーなどによる情報漏洩が過大に評価されるが、現実の生活はビッグデータとAIにより成り立っているとする実例紹介とAIの基礎講習
- (イ)佐賀市のチャットボットによる問い合わせ業務のAI代行や、RESASといった実例紹介
- (ウ)人口減少社会で現行の人手をかけた行政サービスは成り立たなくなる。企画立案、現場対応といった業務以外はほとんどAIで代行可能。
市政への影響、反映、成果等
1.どこでも起こる土砂災害に備える
ハザードマップ作成や自主防災組織の設立は進んでいるが、避難場所などについて、具体にどのような災害でどのような規模の災害を想定しているか、どのように活用するかについては、住民はおろか自治会、自主防災組織でも十分理解されていないのではないか。
あらためて、自分たちの町に起こりうる災害について十分理解を深めたうえで、実例をもとにした図上訓練や指示系統の確立、避難手順など、基本的なことから再構築する必要性を感じた。
2.AIの利活用と自治体
かつて提言して進めた自治体FAQシステムもAIに代行させても問題がない時代に入ったことを実感するとともに、紙と印鑑ベースのシステムを早急に見直さなければ、少子化などによる人出不足と行政ニーズの多様化に対応できない時代は目の前にあることをあらためて認識させられた。
まずは、あやまったセキュリティ認識をあらためるとともにマイナンバーカードの推進を進める必要性を感じる。
手始めにチャットボットの導入と、議会でのペーパレス化を検討すべきと感じた。
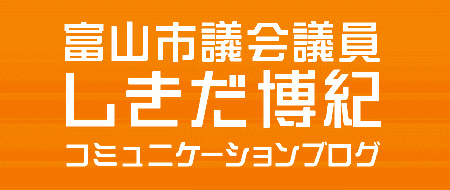
コメント